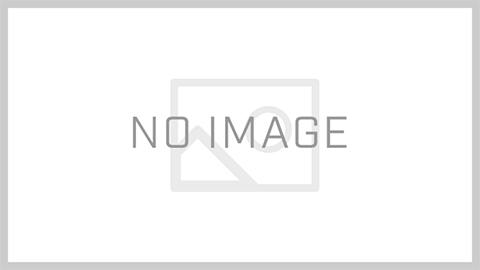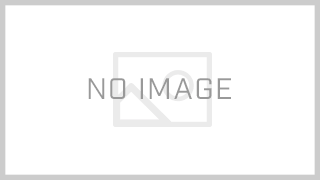いつから「メンヘラ」と口にするようになったのか。
恐らく高校生のときに、常にネガティヴなやつから拾ったのがきっかけ。
「メンヘラ」を知らなければメンヘラにならなかったのに。
「メンヘラ」を用いる奴はメンヘラになりやすい?
“メンタルヘルス・スラング”を用いて、都内に所在する女子大学 の 2 年生以上の学部生 1139 名を対象に、無記名自記式質問票による横断研究を実施した。 1年生と30歳以上の回答者を除外した 455 名を対象とした分析の結果、対象者全体のうち 71.7%の者が用途を問わず“メンタルヘルス・スラング”を用いており、用途を問わず“メンタルヘルス・スラング”を用いる者のうち、82.0%が“メンタルヘルス・スラング”を用いて 自分自身について考えるといったセルフ・ラベリングを行っていた。“メンタルヘルス・スラング”の「使用経験」は、SOC 平均得点が低いことと有意な関連を示し、それは他の変数の影響を調整してもなお認められた。
出典:女子大学生の“メンタルヘルス・スラング”使用と 首尾一貫感覚(SOC: Sense of Coherence)
松崎 良美 2017
要するに、「メンヘラ」や「メンヘラ」に近い言葉を用いる人は、
自身をメンヘラであると認識(セルフ・ラベリング)した経験があり、
経験者は首尾一貫感覚(ストレスを対処する力)が低いそう。
引用した研究は、女子大学生を対象にした調査であることから、
「メンヘラ」に近い言葉を用いる人は〜というのは言い過ぎかも。
ただ、診断コンテンツの利用が増加傾向にある点から、
女子大学生以外に全く当てはまらないわけではないだろう。
え?流行ってない?
「〇〇 診断」でググったこと、あるでしょ。
「メンヘラ」はうつりやすい?
「セカンドハンド・ストレス」の感染力は、見知らぬ他者からより恋人からのほうが強かった(40%)。だが、見知らぬ他者がストレスにあえいでいる映像を見たときも、24%の人がストレス反応を示した
出典:他人がまき散らすストレスに“感染”しない4つの方法
DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー
出典元は海外の論文に関して、日本語で解説されたもので、
ミラーニューロンと派生的に起こるストレスに関して書かれたものである。
「メンヘラ」はうつりやすいと聞くが、
全くの他人からも感染る可能性があるのは問題だ。
だからと言って、メンヘラ化した友人を避けるのも難しいし、
メンヘラ化した友人を避けることでどのような影響があるか、
考えただけでこっちがメンヘラ化しそうになる。
どうすれば「メンヘラ」にならないのか
ストレスに強い人は、
SOC(Sense of Coherence:首尾一貫感覚)が優れているらしい。
ストレスに強いか分かる「SOC」とは
SOCの3要素とは「ストレスへの耐性」を高めるための心理学の理論で、正式には「Sense of Coherence(首尾一貫感覚)」と言います。以下の3つの要素で構成されます。
把握可能感(Comprehensibility)
物事の流れや状況を「理解できる」「見通しが立つ」と感じられる力。処理可能感(Manageability)
自分には「対応できる」「何とかできる」と思える力。有意味感(Meaningfulness)
「やる価値がある」「取り組む意味がある」と思える力。これらが高いほどストレスに強く、健康的に生きやすくなると言われています。
どの要素が一番大事だと思いますか?
ChatGPT 4oに聞いて見たところ、上記の回答をいただきました。
質問で終わるところが、会話上手なAIらしいところ。
mikanでは絶対見ないような英単語と、
中国語っぽく漢字を並べた軽ノリのような専門用語ですが、
これら3要素からなるSOCを鍛えれば、
「メンヘラ」から遠ざかることができるそう。